「このフィギュアの素材、プラスチックって書いてあるけど、PVCとは違うの?」「大切なフィギュアが劣化して溶けるのはなぜ?」そんな疑問をお持ちではありませんか。お気に入りのフィギュアを長く楽しむためには、その素材について正しく理解することが大切です。
多くの方が一度は「フィギュアはプラスチックですか?」と考えたことがあるかもしれません。答えはイエスですが、実は一口にプラスチックと言っても、その種類は様々です。この記事では、フィギュアの素材は何ですか?という基本的な問いに答え、代表的なPVCとの比較を通じて、それぞれの特徴を明らかにします。
さらに、フィギュアの価値を左右する箱の扱いや、経年による劣化の問題、避けたいプラスチックケースの処分方法、そして最終的に「フィギュアはプラスチックごみですか?」という疑問まで、フィギュアとプラスチックに関するあらゆる情報を網羅的に解説していきます。
- フィギュアに使われるプラスチック素材の種類と特徴
- PVCやABSなど主要な素材の違い
- 経年劣化の原因と対策、保管方法
- 正しい捨て方と処分の際の注意点
フィギュアのプラスチック素材に関する基本知識
- そもそもフィギュアはプラスチックですか?
- 具体的なフィギュアの素材は何ですか?
- 代表的な素材であるPVCとは
- 主な素材の特徴を比較してみよう
そもそもフィギュアはプラスチックですか?

はい、現在市場に出回っているフィギュアの大部分は、プラスチックを主原料として作られています。プラスチックは、熱を加えることで様々な形に加工できる合成樹脂の総称であり、キャラクターの繊細な髪の毛の流れや、複雑な衣装のディテールを忠実に再現するのに非常に適した素材だからです。
近年、特にグッドスマイルカンパニーなどの大手メーカー製品で、素材表記が従来の「ABS&PVC製」から「プラスチック製」へと変更されるケースが増えました。
これは、フィギュアの品質をさらに向上させるため、特定の素材に限定せず、ABSやPVCを含む様々なプラスチックの中から最適なものを都度選択できるようにするという、メーカー側の意図の表れと考えられます。
決して品質が低下したわけではなく、むしろ逆で、より良い製品作りのための柔軟な選択肢を確保するための表記変更です。このように、フィギュアとプラスチックは切っても切れない関係にあると言えます。
具体的なフィギュアの素材は何ですか?
フィギュアには、一つの製品の中でも様々な種類のプラスチック素材が巧みに使い分けられています。これは、フィギュアの各部位に求められる特性、例えば強度、柔軟性、透明度などが異なるためです。
最も一般的に使用されるのは「PVC(ポリ塩化ビニル)」や「ABS」ですが、その他にも以下のような素材が目的に応じて選ばれています。
- PMMA(アクリル樹脂): 透明度が非常に高く、クリアパーツやエフェクトの表現に使われます。
- ポリストーン: 樹脂に石粉を混ぜたもので、石のような重量感と高級感が特徴です。重厚なスタチュー(無可動フィギュア)などに用いられます。
- ポリレジン: ポリストーンに似ていますが、より細かな造形が可能です。少量生産のガレージキットなどで見られます。
このように、メーカーはキャラクターのデザインやフィギュアのコンセプトに合わせて、これらの素材を最適に組み合わせることで、魅力的な製品を生み出しているのです。
代表的な素材であるPVCとは

PVCとは「PolyVinyl Chloride」の略称で、日本語では「ポリ塩化ビニル」または「塩ビ」とも呼ばれる、フィギュア製作において最も代表的なプラスチック素材です。フィギュアの本体、特にキャラクターの肌や髪、衣服といった柔らかさやしなやかさが求められる部分に広く使用されています。
PVCの最大の特徴は、「可塑剤(かそざい)」という添加物を加える量によって、素材の硬さを自由に調整できる点にあります。
これにより、硬質でシャープなパーツから、指で押すと少しへこむような軟質のパーツまで、自在に作り分けることが可能です。この加工のしやすさと表現の幅広さが、PVCがフィギュアの主役素材であり続ける理由です。
ただし、この可塑剤はメリットだけでなく、後述する経年劣化による「ベタつき」の原因にもなるという側面も持っています。
主な素材の特徴を比較してみよう
フィギュアに使われるプラスチック素材は、それぞれに異なる長所と短所を持っています。メーカーはこれらの特性を深く理解し、フィギュアの魅力を最大限に引き出すために、パーツごとに最適な素材を選定しています。
ここでは、代表的な4つの素材の特徴を比較してみましょう。
| 素材名 | 主な特徴 | メリット | デメリット/注意点 |
| PVC | 柔軟で加工しやすい、価格が比較的安い | キャラクターの体や髪など複雑な造形に向いている | 経年劣化で可塑剤が染み出し、表面がベタつくことがある |
| ABS | 硬く、耐衝撃性や耐熱性に優れる | 強度が必要な台座、武器、ロボットの関節部などに最適 | PVCに比べると柔軟性に欠け、細かすぎる造形は苦手 |
| PMMA | ガラスのような高い透明度を持つアクリル樹脂 | 透明な髪、エフェクトパーツ、クリアな台座などに利用される | 衝撃に弱く、落としたりすると割れやすい。PVCより高価 |
| ポリストーン | 樹脂と石粉を混ぜた素材で、重く硬い | プラスチックにはない本物の石のような重厚感と高級感がある | 硬くてもろいため衝撃で欠けやすい。高価な大型スタチューに多い |
このように、各素材の特性を知ることで、なぜこのフィギュアの台座は硬いのか、なぜ髪の毛はしなやかなのかといった理由が見えてきます。
フィギュアとプラスチック製品の正しい扱い方
- プラスチック素材の経年による劣化
- フィギュアがベタベタして溶ける原因
- フィギュアの箱は保管すべきか
- フィギュアはプラスチックごみですか?
- フィギュアのプラスチックケース処分方法
- フィギュアのプラスチック素材を理解しよう
プラスチック素材の経年による劣化
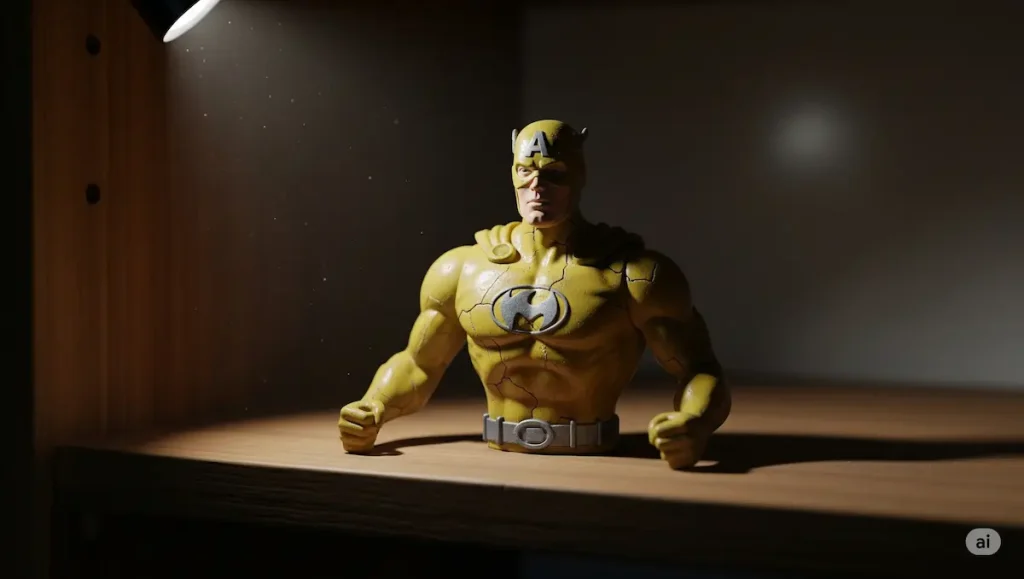
プラスチックを主原料とするフィギュアは、残念ながら時間と共に少しずつ劣化していきます。
これは、素材の化学的な性質によるもので、完全に避けることは困難です。劣化の主な原因としては、「紫外線」「熱」「湿度」の3つが挙げられます。
紫外線による影響
日光や蛍光灯に含まれる紫外線は、プラスチックの色素を分解し、フィギュアの色あせ(退色)を引き起こします。特に窓際に長時間飾っておくと、気づいたときには鮮やかだった色がくすんでしまうことがあります。
熱と湿度による影響
高温の環境は、プラスチックを軟化させ、フィギュアの変形につながる可能性があります。特に夏場の閉め切った部屋や、直射日光が当たる場所は危険です。また、高い湿度は後述するベタつきを促進させる一因にもなります。
これらの劣化から大切なフィギュアを守るためには、直射日光を避け、風通しが良く、温度変化の少ない場所に飾ることが基本です。市販のUVカット機能付きディスプレイケースを利用するのも、非常に有効な対策と言えるでしょう。
フィギュアがベタベタして溶ける原因
久しぶりにフィギュアに触れたら、表面がベタベタしていて、まるで溶けるような感触になっていた、という経験はありませんか。この現象の主な原因は、PVC素材に含まれている「可塑剤」という化学物質にあります。
可塑剤は、硬いPVC樹脂に柔軟性を与え、フィギュアのしなやかな造形を実現するために不可欠な添加物です。しかし、この可塑剤は時間と共に少しずつPVCから分離し、フィギュアの表面に染み出してきてしまいます。この染み出した可塑剤が空気中の水分などと結びつくことで、あの不快なベタつきが発生するのです。
この現象は、特に高温多湿の環境や、箱の中に入れっぱなしで空気が循環しない場所で発生しやすくなります。ベタつきを予防するためには、定期的にフィギュアを箱から出して風通しの良い場所に置いたり、室内の換気を行ったりすることが効果的です。
もしベタつきが発生してしまった場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布や筆で優しく洗い流すことで、ある程度改善することが可能です。
フィギュアの箱は保管すべきか

フィギュアを購入した際、本体を取り出した後の大きな箱をどうすべきか、悩む方は少なくありません。保管場所を取るため捨ててしまいたくなる気持ちも分かりますが、将来的にフィギュアを手放す可能性が少しでもあるなら、箱は必ず保管しておくことを強く推奨します。
その理由は、中古市場において、箱の有無が買取価格に極めて大きな影響を与えるからです。箱はもちろん、フィギュアを固定している内側のブリスター(透明なプラスチック容器)や付属品が全て揃った「完品」の状態が、最も高く評価されます。箱がないだけで、買取価格が半額以下になってしまうケースも珍しくありません。
また、箱は単に価値を保つだけでなく、引っ越しなどの移動時にフィギュアを安全に運んだり、ホコリや紫外線から保護したりする上でも重要な役割を果たします。保管スペースの問題はありますが、これらのメリットを考えると、箱は捨てずに大切に保管しておくのが賢明な選択と言えます。
フィギュアはプラスチックごみですか?
コレクションの整理などでフィギュアを処分する必要が出てきた場合、その捨て方について正しく理解しておく必要があります。
結論から言うと、フィギュアの大部分はプラスチック製品であるため、「プラスチックごみ」として扱われるのが一般的です。
ただし、「プラスチックごみ」の分別方法は、お住まいの自治体によって大きく異なるため、注意が必要です。
- 可燃ごみとして扱われる地域
- 不燃ごみとして扱われる地域
- 資源ごみ(プラスチック類)として扱われる地域
このように、自治体のルールは様々です。処分する前には、必ず市区町村のホームページやゴミ分別アプリなどで、正しい分別方法を確認してください。
また、一部のフィギュアには、台座の軸や関節などに金属パーツが使われていることがあります。自治体のルールによっては、これらの金属部分を取り外して分別する必要がある場合もありますので、併せて確認しておきましょう。安易に判断せず、地域のルールに従って適切に処分することが大切です。
フィギュアのプラスチックケース処分方法

前述の通り、フィギュア本体の処分方法は自治体によって異なりますが、フィギュアを保護している透明なプラスチックケース、通称「ブリスター」の処分についても注意が必要です。
このブリスターは、多くの場合、商品を入れるための容器や包装と見なされ、「プラスチック製容器包装」として分別されることが一般的です。これは、フィギュア本体が「製品」として可燃ごみや不燃ごみに分類されるのとは、異なるルールが適用されることを意味します。
例えば、東京都の一部の区では、フィギュア本体は可燃ごみですが、ブリスターは資源ごみである「プラスチック製容器包装」の日に出す必要があります。
もちろん、これも自治体によってルールが異なりますので、一概には言えません。フィギュアを処分する際は、本体だけでなく、外箱の紙、内側のブリスター、付属品を留めているビニールなど、それぞれの素材を確認し、お住まいの自治体のルールに従って、丁寧に分別することを心がけてください。
フィギュアのプラスチック素材を理解しよう
この記事では、フィギュアとプラスチック素材に関する様々な情報をお届けしました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- フィギュアの大部分はプラスチックを主原料として作られている
- プラスチックは加工しやすく繊細な造形表現に適している
- フィギュアに使われるプラスチックにはPVCやABSなど様々な種類がある
- 最も代表的な素材は柔軟性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)
- 強度が必要な台座や武器には硬いABSが使われることが多い
- メーカーはパーツの特性に合わせて最適な素材を使い分けている
- 近年「プラスチック製」という表記が増えたのは品質向上のため
- 特定の素材に縛られず最適な選択をするというメーカーの意図がある
- フィギュアは紫外線、熱、湿気によって経年劣化する
- 表面のベタつきはPVCに含まれる可塑剤が染み出すことが原因
- ベタつきの予防には高温多湿を避け風通しを良くすることが有効
- フィギュアの箱は価値を保つために保管することが推奨される
- 処分する際は「プラスチックごみ」として自治体のルールに従う
- 可燃ごみか不燃ごみかは地域によって異なるため確認が必要
- 素材の特性や正しい扱い方を理解し大切なコレクションを守ろう








