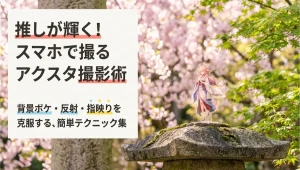フィギュアスタイル運営者の「ぎゅあす」です。
アクリルスタンド(アクスタ)を買うと、必ずセットでついてくる「枠」。コレクションが増えるたびに、このアクスタの枠、どうする?と悩んでしまいますよね。
 ぎゅあす
ぎゅあす私自身、コレクションが増えるにつれて「この枠、かさばるなぁ…」と頭を悩ませる一人です。
何ゴミとして捨てたらいいのか、自治体の捨て方が分からなかったり、かといって保管するには場所を取るし…。
特にデザインが可愛い枠や、作品のロゴがしっかり入っていると、捨てるのは罪悪感もあります。この「捨てられない」気持ち、コレクターなら誰しもが感じることかなと思います。
どうせなら100均アイテムでうまく収納したり、おしゃれな飾り方をしたり、はたまたキーホルダーみたいなDIYで活用する方法がないか探している人も多いかなと思いました。
この記事では、そんな厄介だけど愛着もある「アクスタの枠」問題について、「捨てる・保管する・飾る・活用する」という4つの選択肢を、それぞれ具体的な方法と一緒に網羅的に解説していきますね!
- アクスタの枠の正しい捨て方と分別のルール
- かさばらない保管方法と100均収納アイデア
- 枠ごと飾るディスプレイのテクニック
- 枠をリメイクするDIYやキーホルダーの作り方
アクスタの枠はどうする?4つの選択肢
アクスタの枠に対する悩みは、大きく分けて4つの出口があります。
まずは「処分」や「保管」といった基本的な選択肢から、それぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。ご自身のコレクション量やライフスタイルに合った方法を見つけてみてくださいね。
アクスタの枠、捨て方と分別
私も最初は「これ、どうしよう…」と専用の箱を作って、そこに溜め込むタイプでした。でも、その箱が2つ、3つと増えていった時…「いつかは決断しないといけない」と悟りました(笑)
「捨てる!」と決断した場合、多くの人が直面するのが捨て方ですよね。この問題には、実は2つの側面があるかなと思います。
- 物理的な捨て方:自治体のルールに沿った「分別」の問題。
- 心理的な捨て方:推しグッズを捨てることへの「罪悪感」の問題。
この2つをしっかりクリアにしないと、スッキリと手放すことは難しいかもしれません。それぞれ見ていきましょう。
何ゴミ?正しい処分方法


まず最大の難関が、「これ、一体、何ゴミ?」という物理的な問題です。
アクスタの枠は「アクリル樹脂」というプラスチックの一種。このアクリル樹脂の処分方法は、残念ながら全国一律ではなく、住んでいる自治体によってルールが全く違います。
これは、各自治体の焼却炉の性能やリサイクルの方針が異なるためです。主な分類パターンとしては、以下の3つが考えられます。
- 可燃ごみ(燃えるごみ)
- 不燃ごみ(燃えないごみ)
- プラスチックごみ(資源ごみ)



例えば、ある市では「可燃ごみ」ですが、隣の市では「不燃ごみ」ということも普通にあります。
アクスタの枠は通常サイズが小さいので「粗大ごみ」(一辺が50cm以上など)に該当することは、まずないと考えて良いでしょう。
必ず自治体のルールを確認してください
一番確実なのは、お住まいの自治体のホームページや配布されるごみ分別アプリで、「アクリル樹脂 捨て方」や「プラスチック製品 捨て方」と検索して確認することです。
環境省も、プラスチックごみの分別については「お住まいの自治体の分別ルールに従って」排出するよう呼びかけています。(出典:環境省「市区町村によるプラスチックの分別収集・リサイクル」)
また、ネット検索で「アクリル 処分」と調べると「産業廃棄物」と出ることがありますが、これは飲食店のアクリルパーテーションなど、事業活動で出たゴミのこと。
私たちが家庭で収集したものは「一般ごみ」扱いでOKです。
ごみの分別ルールは法改正などで変更されることもありますので、必ず自治体の最新情報を確認してから処分してくださいね。
罪悪感なく処分する裏ワザ


分別のルールが分かっても、やっぱり「推しグッズ」をゴミ袋に入れるのは心が痛みますよね…。その気持ち、すごく分かります。「ごめんね…」と思いながら捨てるのは、なかなかのストレスです。
この「罪悪感」を解消するための最終手段とも言えるのが、「お焚き上げ」です。
お焚き上げは、思い入れのある品を神社やお寺で供養して焼納する日本の伝統儀式のこと。
昔は人形やお手紙が中心で、プラスチック製品はNGなことが多かったんですが、最近は郵送で依頼できる「お焚き上げサービス」も増えています。
郵送お焚き上げサービスのメリット
こうした専門サービスの良いところは、不燃物(プラスチック、金属パーツなど)も受け付けてくれる場合がある点です。これにより、アクスタの枠だけでなく、例えば金具が取れなくなったキーホルダーなども一緒に供養を依頼できます。
手続きは、専用キットを購入し、処分したいグッズを詰めて郵送するだけ。後日、供養が完了した証明書や動画が送られてくることもあります。
これなら、「ゴミとして捨てた」のではなく「神社でちゃんと供養してもらった」という事実に変わるので、心理的な罪悪感をゼロにすることができます。
私も、どうしても手放せないけど保管場所がない…という「殿堂入り」グッズが増えた時は、この方法を最終手段として検討しています。
お焚き上げサービスは、神社や提供元によって費用や受け入れ可能な品目が異なります。「レターパックで送るだけ」の安価なプランから、箱のサイズで決まるプランまで様々です。
利用する際は、必ず公式サイトでご自身の処分したいグッズが対象か、費用はいくらかを詳細に確認してください。
アクスタの枠、保管方法の鉄則
「いつか元に戻すかもしれない」「フリマアプリで売る時に枠があった方がいいかも」「やっぱりコレクションとして全部取っておきたい」という保管派の人のために、安全な保管方法も解説しますね。
まず知っておいてほしいのは、アクリル素材は結構デリケートだということです。適当に箱に放り込んでいると、後で泣きを見ることになるかも…。特に以下の3つには注意してください。
アクリル素材の3つの弱点
- 日光(紫外線): アクリルは直射日光に非常に弱いです。窓際に置いていると、印刷の色あせや、アクリル自体が黄ばむ(黄変する)原因になります。
- 高温多湿: 湿気の多い場所ではカビの発生リスクがありますし、真夏の車内のような高温環境ではアクリルが変形する(反ってしまう)リスクがあります。
- 摩擦・衝撃: アクリル同士が裸のまま擦れると、表面に細かい傷(スレ)がつきます。これが透明感を損なう一番の原因です。
したがって、保管場所の絶対条件は、「直射日光の当たらない、風通しの良い冷暗所」ということになります。押入れやクローゼットの上段などが適しているかなと思います。
100均でアクスタの枠を収納


じゃあ具体的にどうやって保管するかですが、大量にある枠を効率よく収納するには「省スペース」と「傷防止」が何よりも鍵になります。
一番手軽で省スペースなのは、A4サイズのファイルケースや、ジッパー付きのポリ袋に、枠と本体をセットで入れていく方法です。これなら個別に保護されて傷も防げますし、本棚などに立ててスッキリ収納できます。
推し活収納の定番アイテム
SNSなどの「推し活」界隈では、無印良品のファイルボックスや、セリア・ダイソーといった100均の収納ケースが「〇〇のアクスタの枠にシンデレラフィットする!」とよく話題になりますよね。



こうした定番アイテムを活用するのも、見た目がスッキリ統一されておすすめです。
また、保管とは少し違いますが、お気に入りのアクスタを外に持ち運ぶ(いわゆる「推し活」ですね)場合は、サンリオなどから出ている「アクスタポーチ」も便利です。
多くの場合、本体を入れる透明なポケットと、台座や枠を分けて収納できるポケットが付いており、安全に持ち運べますよ。
アクスタの枠、どうする?飾る・活用術
捨てるのも保管するのも、なんだかしっくり来ない…。どうせなら、この枠も何かに活かしたい!
そんな人は、いっそ「飾る」か「リメイクする」のはどうでしょう?枠も立派な公式グッズの一部。作品ロゴやキャラクターのモチーフがデザインされているなら、活用しないともったいないかもしれません!
アクスタの枠、飾り方の美学


まず紹介したいのが、アクスタの枠を「処分するもの」や「隠して保管するもの」ではなく、「デザインの一部」として捉え直すディスプレイ方法です。
あえて本体を外さず、「外枠ごと飾る」というテクニック。
これは、そのアイテムが「未開封」や「新品」に近い状態(ミントコンディション)であることをアピールでき、コレクターズアイテムとしての「限定感」や「特別感」を強く演出できるんです。
特に、枠自体に作品のロゴやキャラクター名、印象的なモチーフがデザインされている場合は、その効果は絶大。本体だけ飾るより、枠ごと飾った方が世界観が出てカッコいい、なんてこともよくあります。
枠ごと飾るディスプレイ術
この「枠ごと飾る」ディスプレイは、ダイソーやセリアなどの100均アイテムをうまく活用することで、低コストかつ効果的に実現できます。
ダイソーの「神アイテム」で飾る
コレクターの間で特に有名なのが、ダイソーの「ウッドボックス A4サイズマグネット付クリア蓋付」(220円商品)です。
A4サイズのアクスタの枠がピッタリ収まることが多く、これを壁掛けのシャドウボックス(立体額縁)のように飾るのが人気です。マグネット式の蓋が透明なので、ホコリを防ぎつつ中身が綺麗に見えるのが最高ですね。
ただ置くだけでなく、ディスプレイの質を格上げする簡単なコツも紹介します。
テーマやシチュエーションを合わせる
枠に描かれたデザイン(例:作品の舞台、ロゴ)を活かし、関連する他のグッズ(缶バッジやミニフィギュア、ぬいぐるみなど)と並べて、シチュエーションを再現します。
統一感が出て、一つの「作品」のようなディスプレイになりますよ。
「推しカラー」を合わせる
ディスプレイケースの背景や、枠の下に敷く布を「推しカラー」(そのキャラクターのイメージカラー)で統一します。これだけで空間全体に一体感が生まれ、一気に「それっぽく」なります。
ライティングにこだわる
LEDテープライトや小さなスポットライトを使い、ケースを下から照らしたり、後ろから光を当てたりします。
アクリルは光を透過・反射するので、ライティングとの相性が抜群。これだけで、枠のデザインとアクスタ本体が劇的に際立ちます。
アクスタの枠でDIYリメイク


最もクリエイティブな選択肢が、アクスタの枠を「素材」として捉え、全く新しいグッズに生まれ変わらせるDIY(リメイク)です。
まずは初級編として、100均アイテムを使った簡単な「見せる収納」フレームDIYを紹介します。
材料費330円の「見せる収納」フレーム
ダイソーのアイテムを使った簡単なDIYです。持ち運びも可能な自分だけのディスプレイケースが作れますよ!
【材料】
- ダイソー「ウッドボックス A4サイズマグネット付クリア蓋付」(220円)
- ダイソー「カラースポンジシート」(110円)
【作り方】
- ウッドボックスのサイズに合わせて、カラースポンジシートをカッターでカットします。
- スポンジシートの上に、アクスタの枠と本体を配置し、ペンで型取ります。
- 型取った線に沿って、カッターでスポンジシートを丁寧にくり抜きます。
- ウッドボックスにくり抜いたスポンジシートを敷き、該当の穴にアクスタの枠や本体をはめ込みます。
- 蓋を閉じて完成です!
枠でキーホルダーを作る方法
枠のデザインが秀逸な場合、特にロゴ部分やモチーフ部分だけを切り出して、オリジナルのキーホルダーにリメイクするのも人気です。
ただ、この時ぶつかるのが「必要な金具の名前が分からない」問題…。



私も手芸屋さんで「あの、カバンにつけるカチッてやるやつで、クルクル回る…」みたいに聞いた経験があります(笑)
キーホルダーリメイクに必要な主なパーツを、役割と一緒にまとめました。これを見ておけば、手芸店や100均で迷わず探せるかなと思います。
| 必要なパーツ | 目的 | 主な購入先 |
|---|---|---|
| ナスカン | バッグなどに取り付けるための回転式フック金具 | 手芸店, 100均, オンライン |
| 丸カン(マルカン) | ナスカンとアクリル(枠)を繋ぐためのC字型リング | 手芸店, 100均, オンライン |
| アクリルフレーム | 枠の一部をはめ込むための透明なキーホルダー型ケース | FUKUYA ONLINE, ユザワヤ, アニメイトなど |
枠の一部をはめ込む専用の「アクリルフレーム」(通称:はめ込みキーホルダー)を使えば、アクリル自体に穴を開けなくてもキーホルダー化できるので、初心者さんには特におすすめです。
アクリルをカットしたり、丸カンを開閉したりする際には、専用の工具(アクリルカッターや、ヤットコ・ペンチなど)が必要な場合があります。
特にアクリルカッターは普通のカッターと使い方が違うので、ケガには十分注意して作業してください。
上級編:レジンを使った活用法


最もオリジナリティが出せる上級編が、レジン(紫外線硬化樹脂)の活用です。
ここでは、アクスタの枠の「本体が抜けた穴の部分」を、レジンクラフトで言うところの「空枠(からわく)」として利用する専門的なテクニックを紹介します。
推しカラーのラメで埋めたりすると、すごく可愛いオリジナルチャームが作れますよ。
1. 必要な道具リスト
レジンクラフトには専用の道具が必要です。100均でも揃えられますが、仕上がりを気にするなら手芸店のものがおすすめです。
- UV-LEDレジン液(ハードタイプ)
- UV-LEDライト(レジン液を硬化させる機械)
- マスキングテープ(枠の底面を作るのに必須!)
- シリコンマット(作業台の保護)
- ラメ、ホログラム、ビーズ、ドライフラワーなど(封入物)
- エンボスヒーター(気泡を消す。あると仕上がりが格段にキレイに)
- ヤスリ(耐水ペーパーなど。硬化後のバリ取り用)
- ピンセット、つまようじ
2. ステップ・バイ・ステップ手順
基本的な流れはこんな感じです。
- シリコンマットの上で、アクスタの枠(本体が抜けた穴の部分)の裏側に、マスキングテープを隙間なく、空気が入らないようしっかりと貼り付けます。(これがレジン液をせき止める「底」になります)
- 枠を表に向け、穴の部分にレジン液を3分の1ほどの高さまで流し込みます。
- ラメやビーズなど、好きな封入物をピンセットで配置します。
- (あれば)エンボスヒーターの熱風を短く当てて気泡を丁寧に取り除きます。(つまようじで潰してもOK)
- UV-LEDライトを1分~2分照射し、レジンを完全に硬化させます。
- 冷めたことを確認し、裏側のマスキングテープをゆっくり剥がします。
- (もしあれば)縁にはみ出たバリ(余分なレジン)をヤスリで滑らかに整えたら完成です!
レジン作業の注意点
レジン液は素手で触るとアレルギーを起こす可能性があります。作業中は必ず手袋を着用してください。
また、レジン液は特有の匂いがあるため、作業中は必ず部屋の換気を行ってくださいね。
アクスタの枠、どうする?の結論
さて、「アクスタの枠、どうする?」という悩みについて、4つの選択肢を詳しく紹介してきました。
改めて、選択肢をまとめます。
- 【処分する】: 自治体のルールを確認するのが最優先。罪悪感があるなら「お焚き上げ」も検討する。
- 【保管する】: アクリルの弱点(紫外線・湿気・摩擦)を避け、100均ケースなどで省スペースに管理する。
- 【装飾する】: 枠もデザインの一部と捉え、枠ごと飾って「限定感」を演出し、ディスプレイの一部にする。
- 【DIY・活用する】: キーホルダーやレジンで「世界に一つ」のオリジナルグッズにリメイクする。
私自身は、デザインが凝っているお気に入りの枠は「保管」か「DIY」、シンプルなロゴだけの枠や大量にダブってしまったものは、自治体のルールを守って「処分」することが多いですね。



一番もったいないのは、「どうしよう…」と悩みながら罪悪感を抱えて、ただ溜め込んでしまうことかなと思います。
処分する、保管する、飾る、活用する。どの方法でも、ご自身が納得できる方法が一番です。
この記事を参考に、自分に合った方法を見つけて、大切なコレクションライフをスッキリ楽しんでいきましょう!
\ぎゅあす愛用/「あの時ケースに入れておけば…」を未然に防ぐ!
実は私も、昔お気に入りのフィギュアを日焼けでダメにした苦い経験が…。
このブログで紹介しているフィギュア達は、すべて専用のUVカットケースで「完璧な状態」を保っています。
あなたも「飾る」と「守る」を両立しませんか?
\私「ぎゅあす」が本気で選んだ/
次の「神フィギュア」の軍資金、作りませんか?
「これも欲しい…でも金欠…」 その悩み、あなたの「押し入れ」で眠っているフィギュアが解決します。
驚くかもしれませんが、開封済みのフィギュアでも、今なら高値で売れるんです。
適正価格で買い取ってもらい、新しい「推し」を迎える準備をしましょう!
\1円でも高く売る!/